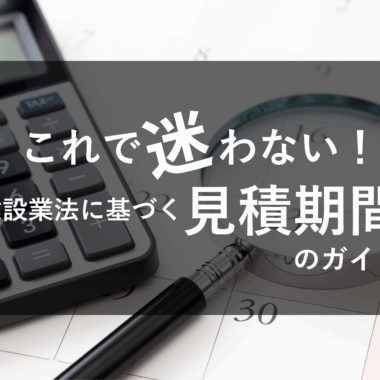はじめに
建物づくりの現場では、内装や外観の華やかさに目が行きがちですが、実は最も大切なのは“見えない部分”である躯体工事です。
柱や梁(はり)、床や壁といった構造体を正確に施工できるかどうかで、建物の安全性・耐久性はもちろん、工期やコストにも大きな影響が出ます。
躯体工事には木造やS造と呼ばれるもののほか、WRC造、RC造という種類があります。
特に、マンション・オフィスビル・商業施設など、大型建築物の多くはRC造で作られています。それらの「骨組み」である躯体の品質は、建物の安全性や耐久性そのものを決めるといっても過言ではありません。
本記事では主に、当社が扱っている「RC造(鉄筋コンクリート造)」の躯体工事についての基本や躯体工事が進む流れ、ポイントなどを初心者向けに分かりやすく解説します。工事内容を理解したい方や建設業界を目指す方にとって、RC造躯体工事の全体像がわかる内容になっています。
目次
- 1.躯体工事とは?
- 2.躯体工事の重要性
ー安全性を左右する基盤の工事
ー工期全体に影響
ー工事の仕上げの細かい部分に直結 - 3.躯体工事の流れ
ー1.山留工事
ー2.土工事
ー3.墨出し(すみだし)
ー4.鉄筋工事
ー5.型枠工事
ー6.コンクリート打設
ー7.脱型・精度確認
ー8.左官工事 - 4.躯体工事の流れを支えるポイント
ー工程の連携
ー精度の積み重ね
ー多職種の協働
ー安全性と耐久性の基盤 - 5.まとめ
躯体工事とは?

工事の中で、建物を支える「骨組み」をつくる工程を躯体工事(くたいこうじ)と呼びます。
RC造の工事では鉄筋を組み、型の中にコンクリートを流し込み固めることで、柱・梁・床・壁といった構造体を形成します。
→RC造についてさらに詳しく知りたい方はこちら!
躯体工事の重要性
安全性を左右する基盤の工事
地震や台風といった外部からの衝撃に耐えるのは建物の構造を支える「躯体」です。鉄筋の配置やコンクリートの品質確保など、一つ一つの管理が建物の安全性に直結します。
工期全体に影響
躯体工事は建設工程の序盤に行われるため、進行が遅れれば後続の内装・設備工事まで ドミノ倒しのように遅延してしまいます。一方で、ここがスムーズに進めば、工期全体の短縮につながります。
工事の仕上げの細かい部分に直結
躯体工事は時として、仕上げ工事そのものになる場合があります。例えば、内装工事で床や壁の施工を行う際に、図面と躯体の寸法の誤差が大きいと、建物の所有者や入居者が所有・使用できる床の面積等が変更になってしまったり、床下に設置する設備に影響が出て排水管が詰まってしまったりと、品質不良に直結する恐れがあります。
躯体工事の流れ

1. 山留工事
地下や基礎をつくるために土を掘ると、周囲の地面が崩れてしまう危険があります。そこで、土が崩れないように板や壁を入れて押さえる工事が山留工事です。地下駐車場や地下鉄工事などでは必須の工程です。
基礎(きそ)とは?
建物の一番下にある“土台”の部分です。建物の重さを地盤に伝える役割を持ち、建物の安定性や耐震性を左右します。RC造や木造、鉄骨造でもまずはこの基礎があってこそ建物が成り立ちます。
ちなみに、躯体工事の前段階として「杭工事」という工事もあります。これは建物を支えるための基礎作りに重要な役割を果たします。
特に地盤が軟弱な場合、コンクリート杭や鋼管杭を使用して地面に強力に固定し、建物の安定性を確保します。当社では山留から上棟までを一括で請け負っておりますが、杭工事も施工可能な範囲として対応ができます。
2. 土工事
建物の基礎をつくるために地盤を整える工事。この時、「捨てコンクリート」と呼ばれる、薄いコンクリートを敷いておきます。地盤を平滑にすることで、後の墨出し(すみだし)等で正確な寸法や位置を把握しながら作業できるようになります。工事のクオリティを上げる下準備として重要な工程です。
3. 墨出し(すみだし)
設計図にある「通り芯(柱や壁等の建物の主要な構造物の基準となる線)」を、予め設計された図面をもとに、現場に原寸で写し出す作業です。測量機器などを使い、数ミリ単位で位置を決定します。ここで誤差が出ると、後の鉄筋・型枠・仕上げまでずれが連鎖するため細心の注意が必要です。建物の位置を決める意味でもとても重要な工程です。
4. 鉄筋工事
柱・梁・壁・床の骨格となる鉄筋を組み立てます。
- 主筋(しゅきん):柱や梁の主要部分を支える鉄筋
- 帯筋(おびきん):柱を補強する横方向の鉄筋
- スターラップ:梁の補強に使う輪状の鉄筋
- 配力筋(はいりょくきん):壁や床に使用される鉄筋
これらを正しく配置し、かぶり厚(鉄筋を覆うコンクリートの厚さ)を確保することで、耐久性・耐火性を担保します。
5. 型枠工事
鉄筋の周りに木製や鋼製のパネル(=型枠)を組み立て、コンクリートを流し込む「型」をつくります。
型枠の固定がゆるいとコンクリートがはみ出して形が崩れる恐れがあるので、以下の金物等でしっかりと固定します。
- セパレーター:型枠の間隔を一定に保つ金物
- フォームタイ:型枠を締め付けて固定する部材
- サポート:型枠の位置を正しい位置で固定する為の部材
- チェーン:サポート同様の用途で使用される副資材
これらを適切に扱わないと流し込まれるコンクリートの圧力によって「はらみ(型枠が外側に膨らむこと)」が発生する可能性があり、寸法不良につながります。
6. コンクリート打設
型枠の中にコンクリートを流し込み、固めることで柱・梁・床・壁が作られます。
機械がなかった昔は竹や棒で打ち付けてコンクリートの中の余分な水分や空気を抜いていたことから「打設」と呼ばれています。現在ではバイブレーターという振動する機械を活用し空気抜き・密実化を行っています。この作業をすることで、コンクリートが固まった後の隙間の発生を防止し、強度を上げることができます。
7. 脱型・精度確認
コンクリートが固まったら型枠を解体し、コンクリートの仕上がりを確認します。万が一凹凸などがあった場合はモルタルというセメントと骨材(例:砂)と水を混ぜ合わせた素材を使い、補修を行います。
8. 左官工事
最後に躯体表面の調整や仕上げ前の下地を整えます。
- 不陸(ふろく):表面の凸凹
これらをモルタルで補修し、防水工事など仕上げ工事の下地を綺麗に整えます。仕上げの品質を左右するため、躯体と仕上げの「橋渡し」の役割を持ちます。
躯体工事の流れを支えるポイント

工程の連携
日本の建設業では昔から「とび・土工、大工、鉄筋」を総称した「躯体四役」や「躯体三役」という言葉がある様に、躯体工事の各工程は独立しているわけではなく、とび(足場)・鉄筋工・型枠大工・コンクリート工といった専門職が連携しながら一体的に進むのが大きな特徴です。
一つの工事が遅れればその後の工事も後ろ倒しになり、コンクリート打設のタイミングもずれてしまいます。
精度の積み重ね
墨出しでの数ミリの誤差が、その後の鉄筋・型枠・仕上げ精度に連鎖します。初期工程の正確さが全体品質を左右します。
多職種の協働
鉄筋工、型枠大工、左官工など、異なる専門職がそれぞれの技術を発揮しつつ、一つの構造体を形にしていきます。また、一つの工事が終わり、次の工程を進める職人に現場を渡す際に行う清掃・片付けも、躯体工事における重要な協働の一つになります。
安全性と耐久性の基盤
躯体工事は建物の「主に外からは見えない部分」ですが、ここでの施工精度や材料品質が長期的な安全性・耐久性に直結します。
まとめ
躯体工事は、建物の安全性・工期・コストを左右する基盤となる工事であり、建設プロジェクトの要です。
現場での正確な作業、施工管理者の徹底したチェック、そして職人たちの技術と連携によって高品質な建物が実現します。
建設業界でキャリアを築きたい人にとって、躯体工事を理解することはまさに「建設の基礎を学ぶ第一歩」と言えるでしょう。