はじめに
「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」って聞いたことはあるけど、正直よく分からない…。
そんな建設会社の方も多いのではないでしょうか。
特に建設業では、「元請」「下請」「孫請」といったように会社同士の関係が複雑です。そのため、法律を知らずに違反してしまうケースも少なくありません。
「下請法なんてうちには関係ない」と思われがちですが、これらを正しく理解しておくことで、
- 元請会社との交渉がスムーズになる
- 不当な減額や支払遅延から会社を守れる
- 契約トラブルを防ぎ、信頼関係を築ける
といったメリットがあります。
法律の内容を知ることは、「身を守る知識」であり、「安定経営に繋がる武器」でもあります。
この記事では、難しい法律の話をできるだけやさしくまとめています。
「下請法の基本」「建設業で起こりやすい違反事例」「守るためにできること」を分かりやすく解説します。
最後には、取引の透明化を助けるツールALLSHAREもご紹介します。
目次
下請法とは?建設業に関わる基本のルール
下請法の目的
下請法は、立場の強い元請会社が、弱い立場の下請会社に不当な要求をしないようにするための法律です。例えば、以下のようなトラブルを防ぎます。
- 「値引きしないと次の仕事を出さない」と言われる
- 納品したのに「やっぱりいらない」と返品される
- 支払をなかなかしてもらえない
このような不公平な取引を防ぐため、下請法では「やってはいけないこと(禁止事項)」を細かく定めています。
建設業で下請法が関係する場面とは?
建設業では「建設業法」と「下請法」の両方が関係してくるため、混同されやすいことが特徴です。
混同されてしまうケースの例
- 工期が遅延した際の責任について、建設業法での契約トラブルなのか下請法違反なのか判断がつかない
- 下請会社が元請会社へ見積書を出したが、元請会社から下請会社への注文書は届かず、建設業法でいう「契約書面義務(契約内容を書面で交わす義務)」の違反なのか、それとも下請法の「書面交付義務」にあたるのか迷う
- 元請会社から下請会社への支払の遅れが発生したとき、建設業法でも指導対象にはなるが、実は下請法の「支払遅延の禁止」にも引っかかる可能性がある
このように、どちらの法律が関係しているか分かりにくい場面が多いのです。混乱を防ぐには、それぞれの法律がどんな目的で作られているのかを知っておくことが大切です。
下請法が適用される条件
下請法は、すべての取引に自動的に適用されるわけではありません。元請会社と下請会社の資本金の差や取引の内容によって適用される対象かどうかが決まります。
条件は以下の2つです。
1. 元請会社が一定以上の資本金を有していて、下請会社が一定以下の資本金である
元請会社のほうが明らかに大きな会社である場合に、下請法が働きます。
資本金要件の目安は以下の通りです。
| 元請会社の資本金 | 下請会社の資本金 |
| 3億円超 | 3億円以下 |
| 1,000万円超 | 1,000万円以下(個人事業者含む) |
例:
・建設会社A(資本金5億円)が、型枠工事を下請会社B(資本金2,000万円)に依頼する
・設備会社C(資本金2,000万円)が、配管工事を個人事業主Dに外注する
このような場合、下請法が適用されます。
2. 取引内容が製造・修理・情報制作・役務提供のいずれかであること
建設業で行われる取引の多くは「役務提供(作業の委託)」にあたります。
例えば次のようなケースです。
- 建築会社が型枠・鉄筋・左官などの工事を下請会社に依頼
- 電気・設備会社が現場ごとの施工や配管作業を別の会社に委託する
- 設計会社が図面やパース作成を外部スタッフに委託する
「作業をお願いしてお金を払う・払ってもらう」関係で、会社規模に差がある場合は、下請法のルールを意識する必要があります。
※「情報制作・役務提供」には対象外となるものもあり、「プログラム作成」「運送・倉庫・情報処理」など限定的なものが政令で定められています。
参考:https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html
建設業でよくある下請法違反の例
下請法違反と聞くと「うちは関係ない」と思う方もいますが、実際には“悪気なく”行われているケースが少なくありません。ここでは、建設業で特に起こりやすい3つのパターンを紹介します。
1. 支払の遅れ・一方的な減額
「検収が終わっていない」「次の現場で調整するから」などの理由で元請会社が下請会社への支払を遅らせたり、根拠なく金額を減らしたりするのは違反です。
事例:元請会社が「出来が悪い」と言いながら根拠を示さず、請求額を10%カット。
→下請法上の「不当な減額」にあたります。
注意ポイント:
検収や品質に問題がある場合でも、元請会社が一方的に金額を変えてはいけません。
まずは契約書や見積書をもとに、双方で再確認することが大切です。
2. 理由のない返品ややり直し
元請会社の都合で、下請会社が作った図面などを一方的に下請会社に突き返したり、費用の負担をせず下請会社に再作成させたりすることも違反です。
事例:元請会社の設計変更によって下請会社は図面の再作成を行うことになったが、再作成にかかる費用を下請会社に負担させた。
→変更の責任が元請会社にある場合、費用は元請会社が負担することが原則です。
注意ポイント:
「注文後の変更」に関して、双方が契約書やメール、チャットなどを用いて、必ず理由と費用負担の取り決めの記録を残しておきましょう。
3. ノウハウや資料の不当利用
下請会社が苦労して作った図面や資料を、元請会社が別の現場で無断使用するのも違反になります。
事例:下請会社が作成した施工図を元請会社が別案件で再利用。報酬もなく無断で使用した。
→「技術資料等の不当利用」として違反に該当します。
注意ポイント:
図面・資料・提案内容などは、知的財産とみなされ、作成者に権利があります。再利用したい場合は、事前に元請会社から下請会社に承諾を取るのが原則です。
参考:https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html
下請法 11類型の禁止事項をまとめました
下請法で定められている「11の禁止行為」は、要するに、「元請会社がしてはいけないことリスト」です。建設業の現場で起きやすいケースを挙げながら紹介します。
| 禁止行為 | 建設業での例 |
| ① 受領拒否 | 着工後、不当な理由で受け入れ(支払)を拒否する。 |
| ② 下請代金の支払遅延 | 支払期日を過ぎても支払わない。 |
| ③ 下請代金の減額 | 理由なく請求額をカットする。 |
| ④ 買いたたき | 「他の会社ならもっと安くやる」と不当に安い単価を押しつける。 |
| ⑤ 返品 | 元請会社の都合で納品済みの資材や図面を一方的に突き返す。 |
| ⑥ 不当な経済上の利益の提供要請 | 広告費や安全協力金を強制的に負担させる。 |
| ⑦ 不当な給付内容の変更・追加 | 追加工事や仕様変更を依頼しておきながら、追加費用を払わない。 |
| ⑧ 不当なやり直し | 元請会社の事情で必要になった設計変更を下請会社の責任にして再施工を求める。 |
| ⑨ 報復的な取扱い | 不当な扱いに抗議した下請会社に対して、次の現場を回さない・契約を打ち切る。 |
| ⑩ 不当な情報提供要請 | 「他社の見積金額を教えて」など、取引と関係ない情報を下請会社にしつこく求める。 |
| ⑪ 技術資料等の不当利用 | 下請会社から提出された図面・資料を無断で別現場に再利用する。 |
これらは「うっかり」でやってしまっていても違反対象になります。違反が繰り返されると、公正取引委員会からの勧告や社名公表に繋がる場合があります。書面やメールで証拠が残る時代だからこそ、言った・言わないのトラブルを防ぐ仕組みが大切です。
違反した場合のリスク
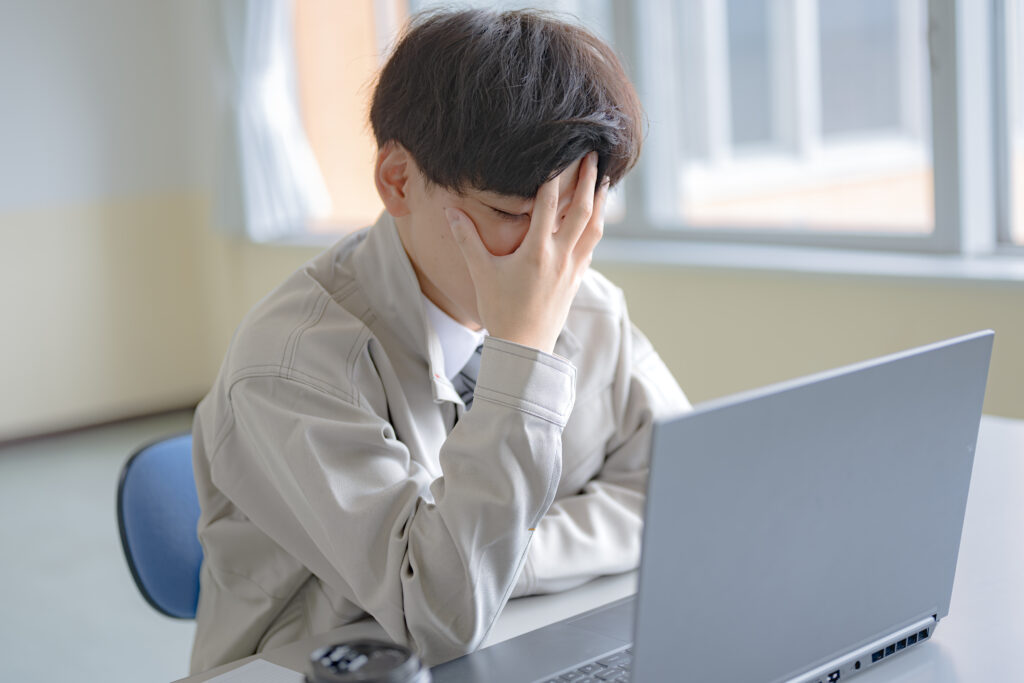
下請法の違反が確認されると、公正取引委員会や中小企業庁から勧告や指導を受けることがあります。内容によっては会社の信用に関わる重大な影響が出ることもあるので注意しましょう。
1. 行政からの指導・勧告
違反が見つかった場合、公正取引委員会や中小企業庁から「改善指導」や「勧告」を受けることがあります。
この段階ではまだ罰金などの恐れはありませんが、改善が見られなかった場合には社名が公表される可能性があります。
社名が公表されると…
- 新しい取引先から「コンプライアンスに不安がある会社」と見られる
- 大手や公共工事の入札でマイナス評価になる
- 下請会社が離れていく
などのリスクがあります。一度の違反でも、信頼を取り戻すのには時間がかかります。
2. 実務上のダメージ
行政処分だけでなく、日常の取引にも影響が出ます。
たとえば…
- 元請会社:信用を失うと、下請会社が集まらなくなる
- 下請会社:注文元からの支払が滞り、キャッシュフローが悪化する
- 双方:現場の雰囲気が悪くなり、人材の定着にも悪影響
つまり、法律違反=経営リスクでもあるのです。日頃からルールを意識して取引管理を行いましょう。
下請法を守るための実務チェックリスト
- 契約や注文内容は必ず書面で残す(メール・電子契約でもOK)
- 支払期日を明確にし、社内で共有
- 追加工事の費用負担は必ず合意を取る
- 下請会社の図面・資料は無断で使わない
- 取引履歴を管理できる仕組みを導入
下請法を知ることがトラブル防止の第一歩!
下請法は「元請会社を縛るルール」ではなく、お互いの信頼を守るためのルールです。
この法律を正しく理解しておけば、無用なトラブルを防ぎ、安定した取引関係を築くことができます。
とはいえ、実際の現場では「注文書を出し忘れた」「支払期日を勘違いした」など、ヒューマンエラーが起きがちです。
そうしたリスクを減らすには、管理を“見える化”する仕組みが大切です。
ALLSHAREで“見える取引”を実現しよう
ALLSHAREは、建設会社向けに作られた原価管理システムです。
工事ごとの注文・支払などをデータで一元管理できるので、下請法の「書面交付義務(=注文内容の記録)」や「支払期日管理」を意識しながら原価管理ができます。
- 支払期日・取引履歴を記録できる
- 注文書などの書類をデータで管理
「うっかり違反」を防ぎながら、健全な取引を続けられる環境づくりを可能にします。法令遵守と粗利の管理、どちらも両立させたい会社におすすめです。





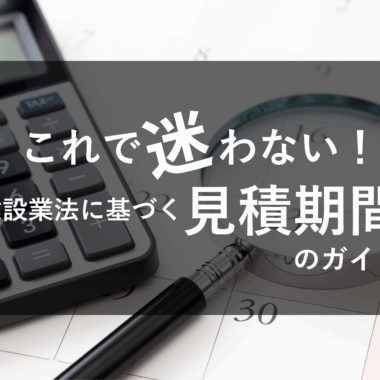
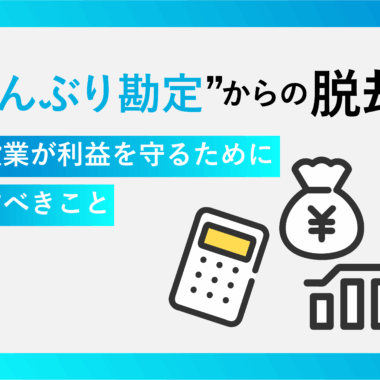

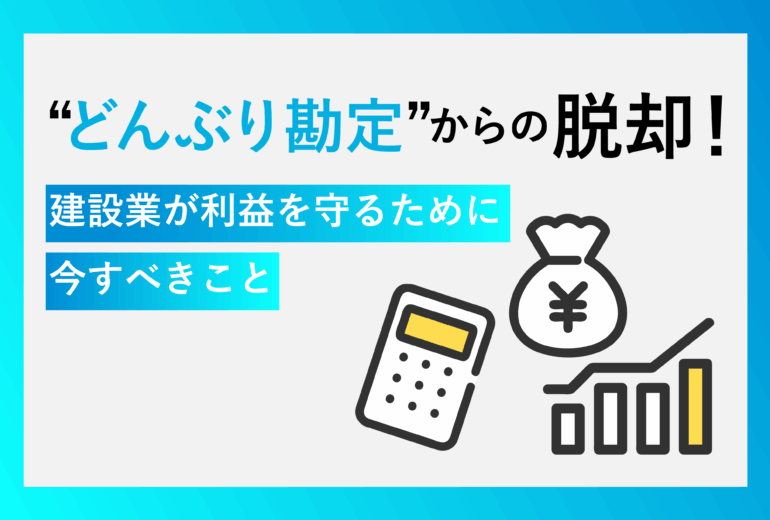

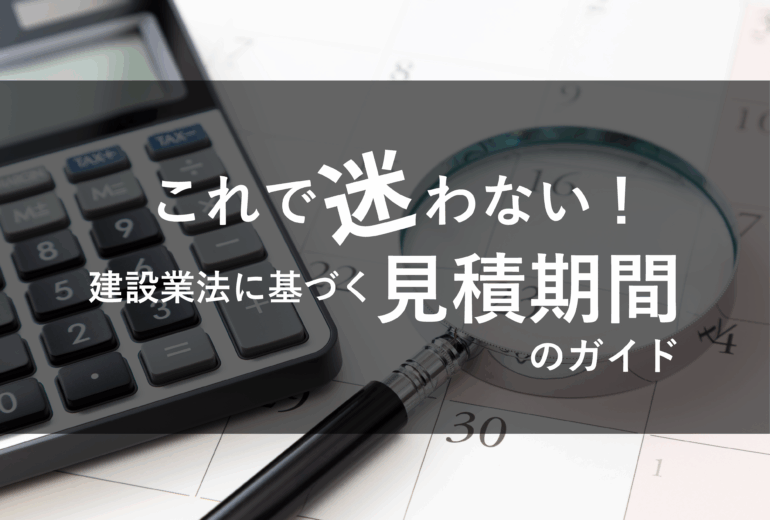
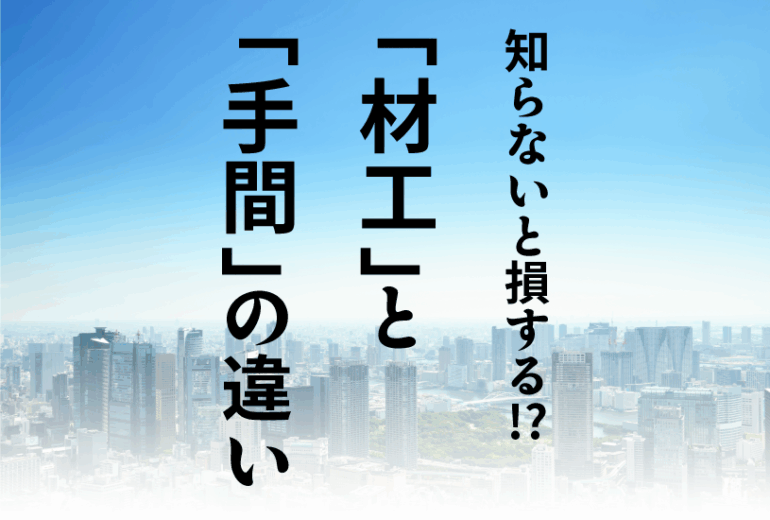


コメント